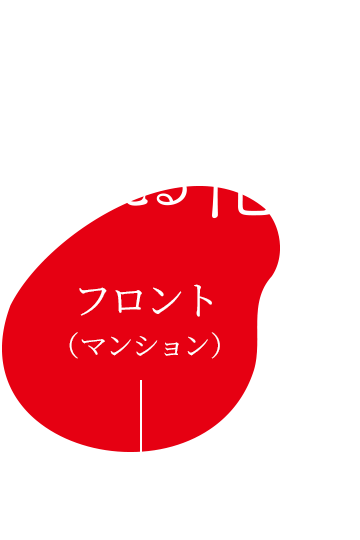プロジェクト概要
「良いマンション」はどのようなものでしょうか。マンションの管理状態の良し悪しは、「良いマンション」を見分けるための有効な材料になるはずです。2022年に開始したマンションの管理状態を客観的に認定・評価する制度を通じて、今までとは違うアプローチからマンションの資産価値向上に取り組んだプロジェクトを紹介します。

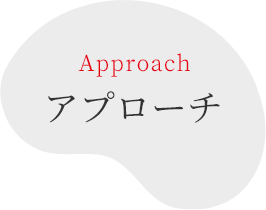
マンションの管理状態を
可視化する
二つの新制度が開始。
マンションの良し悪しを客観的に判断するためには何かしらの指標が必要です。近年、高経年マンションの管理不全が問題視されるケースも増えていますが、マンション市場を活性化させるためにはマンションの管理状態を適正に評価する仕組みが求められていました。そこで国と地方公共団体は一定の基準を満たすマンションの管理計画を認定する「マンション管理計画認定制度(以下、認定制度)」を2022年に開始。また同年、一般社団法人マンション管理業協会においても、マンションの管理状態や管理組合運営の状態を6段階で評価してインターネット上で情報を公開する「マンション管理適正評価制度(以下、評価制度)」を開始しました。いずれも第三者がマンションの管理状態の良し悪しを判断できるという点では同様の意義があり、当社としても管理物件の両制度への登録を進めたいと考えていましたが、登録したからといってすぐに明確なメリットを得られるわけではありません。これらの制度の意義を管理組合に理解してもらい、制度登録を推進するという点に課題がありました。
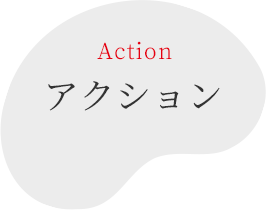
目に見えない価値を、
どのように提案すべきか。
どのようなマンションに対して、どのように制度登録の提案を行うべきなのか、部署の中でも意見は分かれました。「高経年のマンションに提案すべき」「築浅のマンションでも優良認定を受けることには意義がある」などの意見もありましたが、私自身としては、築年数に関わらず、自分たちのマンションの資産価値に高い関心を持つ管理組合に提案しようと考えました。各制度は管理不全への問題意識から始まったものとはいえ、当社が責任を持って管理しているマンションである以上、そこに管理不全の警鐘を鳴らすのは矛盾があるように感じたからです。一方で当社が管理しているからといって簡単に良い評価を得られるわけではありません。「自分たちは良いマンションに住めている」と居住者の皆様に喜びを感じていただくことをゴールにしながら、関心を持っていただけそうなマンションの管理組合には何度も提案を重ねていきました。また、認定制度にしても評価制度にしても、適合認定や高評価を得られるよう、管理状態をより良くしていく取り組みも進めました。

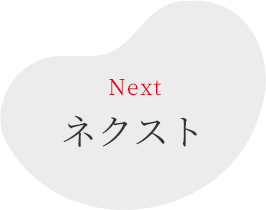
安心して
そのマンションに住まう
理由にもなる。
最初から予測できた通り、管理組合に提案してもすぐに制度の意義を理解してもらえるものではありませんでしたが、私はマンションの資産価値が上がると信じて提案を続け、認定制度では年間4棟、評価制度では年間3棟のマンションを登録することができました。制度登録のメリットは短期的に得られるものではなく、私がフロントとしてそのマンションを担当している間には価値が見いだせないかもしれませんが、いずれ買い手・売り手に動きがあった時には、制度登録を通じて客観的に管理の健全性が担保されることでより買いやすい・売りやすいという価値が生じてくるはずです。また、売買だけに主眼を置いたものではなく、第三者から見て管理状態の良いマンションであるということは、より安心してそのマンションに住める理由にもなります。マンションの資産価値向上という私たちのミッションに対して、これまでとは違う側面からアプローチできたエピソードです。

入社動機
フィットネスクラブ運営会社でインストラクターとして勤務した後、本社部門で人事・総務を経験し、その経験から設備点検会社に勤務。そこでマンション管理の仕事を知り、管理業務主任者資格を取得した後にマンション管理業界への転職を決意しました。前職では複数の管理会社との接点がありましたが、一番レスポンスが早いと感じたのが三菱地所コミュニティでした。レスポンスが早いということは、担当者が適正業務量で仕事ができているということであり、職場環境が整備された会社として期待でき好印象をもったことから当社を志望しました。
「フロント職」の魅力
一人ひとりの裁量が大きく、自分の学んできたことや提案を具体的な形にできるチャンスが数多くあります。制度登録の話がまさにそうだったように、フロントと一言でいっても全員が同じ考え方や行動をするわけではなく、会社方針を踏まえながら自分のスタイルで管理組合と向き合うことが可能です。また、課題解決のアプローチなどをフロント同士で共有するなど、他のフロントから学べる機会も豊富にあります。